今回は、人が快適に感じる空間を設計するために欠かせない「パーソナルスペース」について、姿勢ごとの違いに焦点を当てて詳しく見ていきましょう。
姿勢とパーソナルスペースの関係をマスター!
一級建築士試験では、人が快適に過ごせる空間を設計するための知識が問われます。その中でも重要なのがパーソナルスペースの概念です。パーソナルスペースとは、人が他人に近づかれると不快に感じる、心理的ななわばりのことです。この空間は、文化や個人差、状況によって異なりますが、一般的には以下の4つの距離帯に分けられます。
-
密接距離 (intimate distance):0~45cm。恋人や家族など、非常に親しい間柄の人に許される距離です。
-
個体距離 (personal distance):45~120cm。友人や知人との会話に用いられる距離です。
-
社会距離 (social distance):120~350cm。仕事上の関係や、初対面の人とのやり取りに適した距離です。
-
公衆距離 (public distance):350cm以上。講演者と聴衆など、公的な場面で保たれる距離です。
建築の設計では、これらの距離を考慮して、人がストレスなく過ごせる空間を創出する必要があります。
姿勢によるパーソナルスペースの変化
パーソナルスペースの広さは、人の姿勢によっても変化します。特に一級建築士試験では、以下の3つの姿勢がよく出題されます。
立位(立った状態)
立った状態では、人のパーソナルスペースは最も広くなります。これは、立ち姿勢が最も警戒心が高く、移動しやすい状態であるためです。公共空間や駅のホームなど、人が混雑する場所では、この立位のパーソナルスペースが確保できるように設計することが重要です。
椅座位(椅子に座った状態)
椅子に座った状態では、立位に比べてパーソナルスペースは狭くなります。座っていることで移動が制限され、リラックスした状態になるためです。カフェやレストラン、オフィスのミーティングスペースなどでは、この椅座位のパーソナルスペースを考慮して、隣席との距離を適切に設定する必要があります。
平座位(床に直接座った状態)
床に直接座る平座位(正座やあぐらなど)では、パーソナルスペースは最も狭くなります。これは、座卓を囲んで食事をする、茶道を行うなど、親しい間柄や特定の文化的な状況で用いられる姿勢だからです。日本の和室や、旅館の広間などの設計では、この平座位の特性を理解して空間を計画します。
まとめ
一級建築士試験では、立位 > 椅座位 > 平座位の順でパーソナルスペースが狭くなることを理解しておきましょう。この知識は、オフィスや商業施設、住宅など、さまざまな建物の設計問題に応用できます。特に、人と人との距離が重要になる動線計画や、家具の配置計画の問題で役立ちます。
免責事項
本記事は一級建築士試験の学習を補助する目的で作成されており、特定の試験問題の出題を保証するものではありません。学習においては、必ず公式のテキストや過去問題、最新の法規をご確認ください。
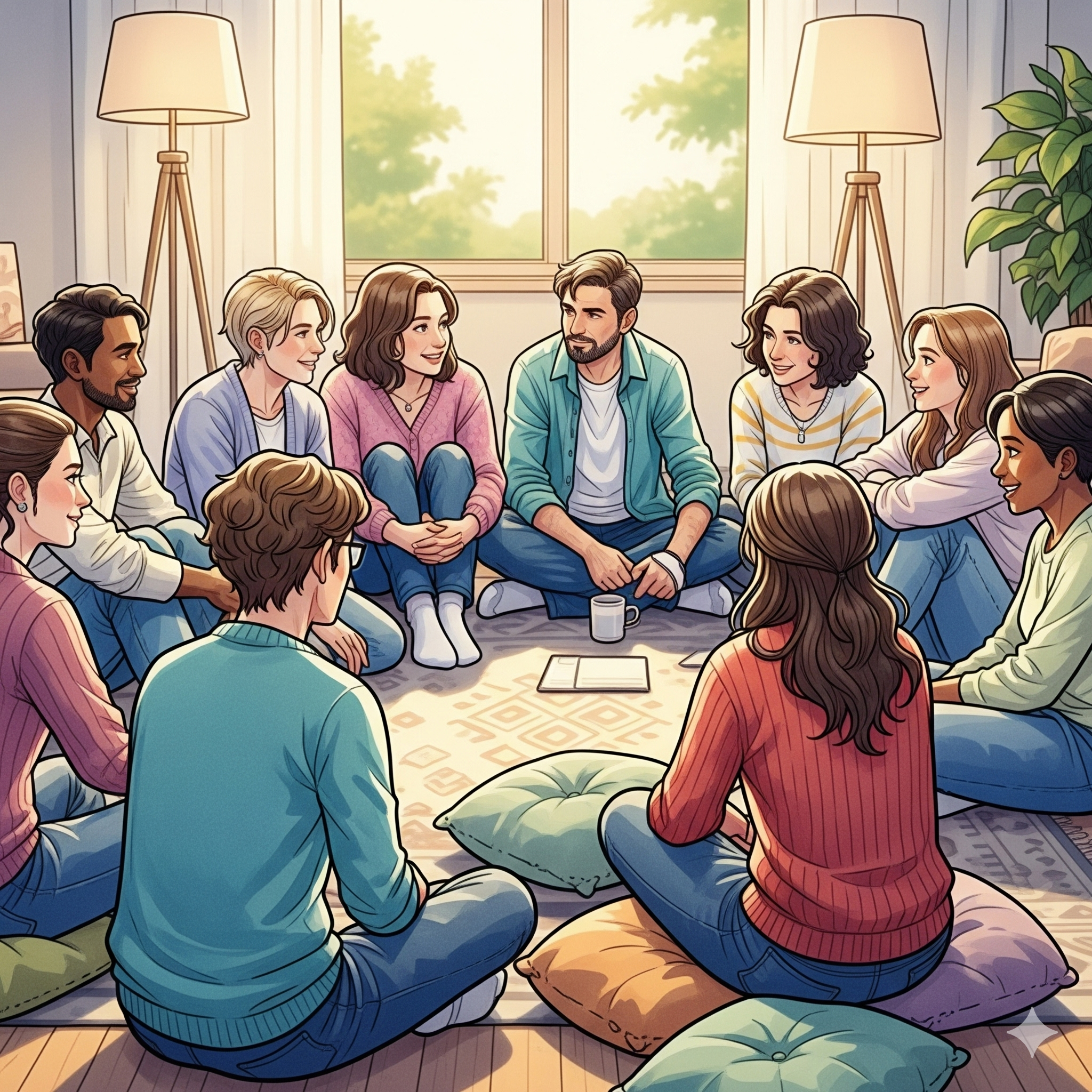


コメント